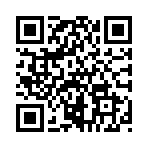☆野球を通して、子供たちの未来を創造する!☆
近年、甲子園やプロ野球の盛り上がりの裏で、野球の競技人口の減少が顕著に表れており、中学校体育連盟のデータによれば、軟式野球部競技人口は2009年31万7,053人から、2016年には12万人減の18万5,413人まで減少しています。
一方サッカーは23万人前後で推移しており、既にサッカー部員数が野球部員数を上回っている現状があります。特にジュニア世代(7才~15才)における競技人口の減少は深刻な問題となっています(全国の少年野球チームが過去5年間で200チーム減少しています)。
スポーツの多様化、ボール・バットの過敏な危険認識による公園や校庭でキャッチボール禁止、高額な道具代や当番で親の負担が大きく、子供にあえて野球をさせないなど「野球」に触れる機会が失われ、野球を知る・始める子供が少ないと言う理由にあげられます。
野球を通して、幼少期の子供たちにスポーツを始める機会を与え、子供の心身の健康増進の機会をつくり、また、野球の楽しさを伝える事により、将来の野球の競技人口増加に寄与する事を目指しています!
NPO法人野球未来.Ryukyu 理事長 : 大野 倫
_1.png)
_1.png)
2019年06月05日
大野倫コラム「野球の力」 2

3回戦から決勝まで4日連続4連投(決勝:大阪桐蔭戦)
子供たちと楽しく野球遊び
最近、高校野球の球数制限についての取材をよく受けます。28年前の甲子園4連投(6完投)、故障で選手生命の危機が負の教材として、今の高校野球のあり方、制度について意見を求められます。「燃え尽き甲子園」の代表格として自負もあり、率直な想いを述べています。各方面から遠路沖縄まで取材に来て頂き感謝ですね。
高校野球も昨年100年を迎え、未来を見据えた過渡期に入りました。近年は改革が進められ、選手ファーストの取り組みが議論されるようになりました。特に投手は球数制限導入の機運が高まっていますが、イニング制限か球数か、世界基準に習ってルールとして採用されていくでしょう。ただ、そこにはやはり「勝負」があります。小学生でも高校生でも、競技である以上、勝ちたいんです。勝ちたい思いは100年先も変わらないです。僕も今中学生を指導していますが「勝ちたい!」気持ちに変わりはありません。負けていい試合なんてありません。
『勝利と育成の両立』
スポーツ界の永遠のテーマですね。「どう戦うか」「どう起用するか」は指導者に委ねられるところが大きいです。そこにルールがあれば、ルールに則って戦うことができます。いや、戦うしかありません。勝つためにオーバーワークした選手、オーバーヒートした指導者を抑制することができます。曖昧なルールが、サイン盗みや酷使など時代と逆行するプレーを起こさせているのです。
『パフォーマンスで感動を呼ぶ』
疲弊した選手が泥まみれになって、怪我をおして戦い抜く姿はやはり感動します。例えば、大谷翔平選手が連戦連投で迎えた決勝戦、130kの速球しか投げられず、グラウンドで散る姿も感動を呼ぶかもしれません。半面、休養とルールによって、決勝戦で160kの速球を連発する大谷選手が躍動する姿も大きな感動を呼びます。
どちらの感動を選択しますか?僕は後者を見たいです。
小さい頃は、清原さんのどこまでも飛んでいくホームラン、伊良部秀樹さんの剛速球に憧れました。子供たちは選手の汗以上に、ハイレベル、ハイパフォーマンスの選手に「夢」を見ます。選手たちに良い環境を与えれば、「今日は何キロ出るんだろう」「でかいホームラン見たい」わくわく感を子供たちやファンに与えることができます。
子供たちが野球に夢を抱く環境を整えることが、次の100年の野球界の発展に繋がると確信しています。
「後ろを振り返りながら前に進む」大事ですね!
Posted by ⚾野球未来プロジェクト at 13:58
│大野 倫コラム「野球の力」